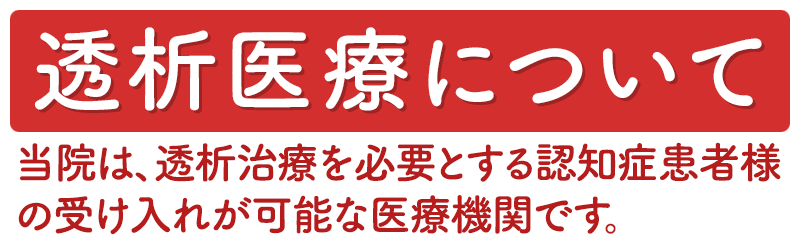
![]()
![]()
第27回日本老年学会総会―その3― の続きです。
日本老年精神医学会の6月17日のシンポジウム
「認知症医療における精神科医の役割」では、
上川病院理事長 吉岡充先生の「我が国における老年精神科医の役割」を聴きました。
 上川病院は、日本で最初に認知症の患者さんを治療に際して縛らない、
上川病院は、日本で最初に認知症の患者さんを治療に際して縛らない、
「身体拘束廃止」に踏み切った病院として知られています。
吉岡先生が書かれた文章は時々目にしますが、ご本人の発表を聴いたのは初めてでした。
「抑制死」
という吉岡先生が提唱した概念についても直接お話をうかがうことでよく理解できました。
同じシンポジウムで、
国立長寿医療研究センター精神科医長服部英幸先生が
「地域の認知症医療と高齢者専門病院の役割」
というタイトルで発表されました。
重篤な内科合併症を持つ認知症の患者様の入院治療を担っているそうで、
病院の役割としては飯能老年病センターに近い病院かな、と思いました。
ただ、国立長寿医療研究センター病院は300床の病院で医師が60人もいるそうです。
国立ならではの余裕とも言えますが、経営的に成り立っているのかな?
という疑問もありました。
このような国立病院(独立行政法人)がある愛知県大府市の市民は幸せですね。
学会ではロビーなどに臨時の本屋さんができて、医学関係の本を販売しています。
医局Y.M
他の学会参加記はこちら